PCストレステストツールとして知られるOCCTのバージョン15がリリースされ、マイクを使用せずにコイル鳴きを検出する新機能が追加されました。この機能は、コイル鳴きを特定のメロディーに変換することで、騒音の多い環境でも音源を特定できるようになります。
コイル鳴きをメロディーに変換して検出
OCCTの新しいコイル鳴き検出機能は、マイクを使用せずに動作します。この機能を使用すると、OCCTは「3D Adaptive Configuration」の一つの機能としてシステムに意図的に負荷をかけ、3種類の事前定義されたメロディーのいずれかを生成します。
従来のコイル鳴きは一定の高音として聞こえるため、周囲の環境音に紛れて音源の特定が難しい場合がありました。しかし、この機能により特定のメロディーに変換されることで、環境音の中でもコイル鳴きが目立つようになり、音源の特定が容易になります。
負荷で発生すると言うコイル鳴きのメカニズムを活用
コイル鳴きは、PCのグラフィックスカード、電源ユニット、マザーボードなどのコンポーネントで発生する自然現象です。音が高音で目立つケースもあるため、一度気付くと不快に感じられることがあります。
この現象は、対象のコンポーネントに負荷がかかるほど音が大きくなる傾向があります。また、高負荷と低負荷の間で電力が急速に変動する場合にも音が発生しやすくなります。そのため、多くのユーザーがゲームプレイ中、特に300~1000FPSといった非常に高いフレームレートで動作している際にコイル鳴きを経験するのは、このような負荷変動が原因です。
コイル鳴きの発生は一貫性がなく、同じメーカーの同じモデルであっても個体差があります。また、発生する条件も異なり、中程度の負荷時のみコイル鳴きが発生する製品もあれば、フル負荷時やアイドル時のみ発生する製品もあります。
OCCTはこの負荷で音が発生するメカニズムを活かして、グラフィックカードに対して高負荷と低負荷の間で急速に切り替えることで、コイル鳴きの音量や音程を制御します。また、この負荷の切り替えパターンを調整することで、コイル鳴きを3種類の事前定義されたメロディーとして出力させることが可能になります。つまり、負荷のオン・オフのタイミングと強さを制御することで、一定の高音だったコイル鳴きを特定の音楽的なパターンに変換するという仕組みになっています。
どんなユーザーに有用な機能なのか?
この機能が特に役立つのは、オフィスやネットカフェなど、周囲の騒音が大きい環境です。通常の方法ではコイル鳴きの音源特定が困難ですが、この機能を使えば、メロディーとして聞こえるため、グラフィックカード、電源、マザーボードのどれが音源なのかを判別しやすくなります。
一方で、寝室など静かな環境でPCを使用しているユーザーにとっては、コイル鳴きは容易に検出できるため、この機能の必要性は低いでしょう。
ただし、PCから異音が聞こえている場合、その音がコイル鳴きなのか、それともファンのベアリング不良など他の異音なのかを判断する際にも役立ちます。そのため、トラブルシューティングツールとしても有効な機能になっています。
実際に音がするかは個体差が大きめ
筆者の手持ちのグラフィックカード(GeForce RTX 5090とRadeon RX 9070 XT)で同機能を試したところ、特にコイル鳴きやメロディーらしきものは一切聞こえませんでした。
また、このコイル鳴きを発生させるモードは負荷を与えることから、実行時にはGPU温度が上がり、ファン回転数も上がります。そのため、小さいコイル鳴きであればファンノイズにかき消されている可能性もあります。
この結果から、実際にこの機能でコイル鳴きが検出できるかは、グラフィックカードの個体差に大きく依存すると考えられます。コイル鳴きが発生しやすい個体を持っている場合には有効な機能ですが、そもそもコイル鳴きが発生しない個体では恩恵を受けられません。







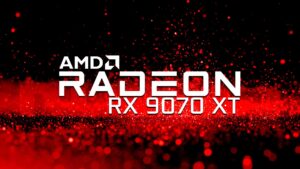



コメント