AMDは2026年に発売されるZen 6アーキテクチャーの後継CPUとしてZen 7アーキテクチャーの投入を計画していますが、今回このZen 7を採用する製品に関するリーク情報が登場しました。
AMD Zen 7アーキテクチャーのリークが登場。2028年以降に登場予定
AMDは約2年置きにアーキテクチャーの刷新を実施しており、2024年に発売されたZen 5の後継であるZen 6は2026年に発売される予定です。そして、Zen 6の後継であるZen 7は順当にいけば2028年発売が計画されていると考えられ、AMD内でも設計に着手している時期になりますが、今回2028年に発売が予定されているZen 7アーキテクチャーを採用するCPUについて、リーカーのMoore's Law is Dead氏がZen 7採用のデスクトップからノートPC向けに計画されている製品の情報を明らかにしました。
Zen 7はTSMC A14プロセスを採用。電力効率の大幅向上が計画される
AMDのZen 7アーキテクチャーはEPYCで採用される製品とコンシューマー向けでコア構成が異なっているとのことで、EPYCで採用されるCPUダイはSteamboatと呼ばれます。一方で、コンシューマー向け製品は「Grimlock」と呼ばれるとのことです。
サーバー向けのEPYCやデスクトップやノートPC向けRyzenなどほぼすべての製品でTSMC A14プロセスを採用することが計画されているようです。
これにより、コア数がZen 6から増えるほか、電力効率の大幅向上、キャッシュ容量の拡大も可能となる見通しで、L2キャッシュはZen 4以来据え置かれていた1MBから2MBに拡大されます。
Zen 7のデスクトップ向けはソケットAM5に対応。最大32コアに加え3D V-Cacheモデルは合計224MBのキャッシュ搭載
AMDのデスクトップ向けZen 7はGrimlock Ridgeと言うコードネームの基開発され、最大16コアと8コアを持つCCDが開発中です。
16コアを持つCCDは32MBのL2キャッシュと64MBのL3キャッシュを備えることで合計96MBのキャッシュ容量を持ちます。また、3D V-Cacheにも対応する計画で、3D V-Cache側には最大160MBのキャッシュを追加し、CPU合計で224MBのL3キャッシュを備える構想とのことです。
なお、この16コアのCPUダイはRyzen向けに開発されるCCDとしては過去最大サイズの98mm2になる見込みでコストはかなり高くなる見通しです。なお、同CCDは一部のEPYCにも採用されるようです。
8コアを持つCCDはL2を16MB、L3を32MB備えることで合計48MBのキャッシュ容量を持ちます。なお、同CCDはコストや電力効率優先で開発されていることから、3D V-Cacheへは非対応の設計とのことで、ノートPC向けのGrimlock PointやGrimlock Haloにも採用される製品になります。
デスクトップ向けは最大32コア化。ソケットAM5にも対応
Zen 7は現行のZen 5などと同じくデスクトップ向けはCCDを最大2基搭載できる設計になっているため、ハイエンドモデルでは合計32コアを備えることができ、デュアル3D V-Cacheの場合はCPU合計で448MBのL3キャッシュそ備えることが出来ます。
Zen 7はCCDは新規設計となりますが、I/OダイはZen 6のものを流用するためソケットAM5に引き続き対応する見通しで、実際にZen 7がソケットAM5対応となれば同ソケットは少なくとも6年は新製品をサポートするなどソケットAM4以上に長寿ソケットになることが予想されます。
ノートPC向けZen 7は電力効率が大幅向上
ノートPC向けZen 7はGrimlock Pointと呼ばれ、性能重視のZen 7 Classicを4コアと効率重視のZen 7cを8コア備えたハイブリッドコアとなり、合計12コアを備えます。ただ、これに加えて低電力コアも備える予定ですが、具体的なコア数は不明とのことです。
また、このGrimlock Pointは追加でデスクトップ向けにも採用されている8コアCCDを加えることが可能で、これらを合計すると20コア構成も実現できるようです。
なお、このGrimlock Pointは電力効率の向上が焦点に当てられており、Zen 6に比べて電力辺りの性能が以下の通り向上させることが目標のようです。
- 22WでZen 6に対して13~17%性能向上
- 12WでZen 6に対して20~25%性能向上
- 7WでZen 6に対して26~32%性能向上
- 3WでZen 6に対して30~36%性能向上
特に低消費電力時の性能向上が凄まじく、省電力性能に優れるARMでノートPC向け市場に挑もうとしているQualcommやNVIDIAを意識していることが明白です。
Grimlock Haloは最大36コア構成。内蔵GPUは現時点で不明
AMDはGrimlock Haloと呼ばれる内蔵グラフィックス性能を大幅強化したStrix Haloと同じHaloシリーズを用意する見通しで、標準構成はZen 7 Classicを8コアとZen 7cを12コア備えたハイブリッドコアで20コア、さらに8コアを備えたCCDを2基追加することで合計36コアまで対応します。
なお、現時点でGrimlock HaloやGrimlock Pointに採用される内蔵GPUは明らかにされていません。ただ、RDNA 5が2027年頃に登場すると言われているため、保守的な開発計画の場合はRDNA 5を流用し、挑戦的な開発計画でもRDNA 5.5など改良版に留まると考えられます。
発売時期は2028年以降
AMDはZen 4を2022年、Zen 5を2024年に投入しており、次世代CPUのZen 6を2026年以降に投入するなど2年置きにCPU製品の刷新を行っています。このスケジュールはAMDの収益源であるサーバー、データセンター向け市場で競争力を保つために必要な間隔であるため、Zen 7もZen 6発売から2年後に当たる2028年に発売すると見られています。
なお、リークではZen 7 EPYCを2028年上半期に投入し、そのあとにコンシューマー向けRyzenを発売するとのことですのでZen 7のデスクトップ向け製品が見られるのは2028年後半になると考えられます。
AMDのCPU開発戦略を読み解くと、同社の技術革新がサーバー・データセンター向け市場における競争環境に大きく牽引されていることが分かります。
AMDはサーバーからデスクトップ、ノートPCまで基本的なアーキテクチャーを共有する開発体制を採用しており、特にCCDチップレットはサーバー向けEPYCとデスクトップ向けRyzenで非常に近い設計となっています。この統一されたアーキテクチャー戦略により、AMDは開発コストを効率化しながらも、収益の大半を占めるサーバー・データセンター市場で求められる最先端の性能を追求できる体制を構築しています。
現在、サーバー・データセンター市場ではQualcommやBroadcomといった競合が参入を図っており、一部の大手企業は自社開発のカスタムCPUに移行する動きも見られます。こうした競争圧力に対抗するため、AMDは同分野に多額の研究開発費を投じており、その結果生まれた技術革新が、いわば「おこぼれ」としてコンシューマー向け製品にも波及しています。Zen 7で計画される最大32コアのデスクトップCPUや224MBという巨大なキャッシュ容量は、まさにこの戦略の成果と言えるでしょう。
一方で、ノートPC向け製品は異なるアプローチが取られつつあります。今回のリークで明らかになったGrimlock Pointの電力効率目標、特に低消費電力時における30%以上の性能向上という数値は、QualcommやNVIDIAといったARM系チップとの競争を強く意識したものです。x86アーキテクチャーでありながらARM並みの電力効率を実現しようとするAMDの姿勢は、ノートPC市場におけるアーキテクチャー競争の激化を物語っています。
ただし、この挑戦的な計画には懸念材料もあります。現在のAIブームを背景にサーバー向けCPU需要は絶好調ですが、今後数年以内にこのブームがピークアウトした場合、サーバー市場の需要減退に伴いR&D予算の縮小やコストダウンを目的としたスペック抑制などの可能性も否定できません。Zen 7の16コアCCDが過去最大の98mm²というダイサイズになる見込みである点も、製造コストの観点から市場環境の変化に脆弱な要素となり得ます。
そのため、2028年という発売時期を考えるとまだまだこの計画通りにZen 7が登場するかは確実ではありませんが、Zen 4やZen 5のみならずZen 6からの乗り換えでも大幅な性能向上が期待できそうですので、今後の動向が注目されます。






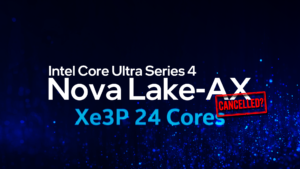

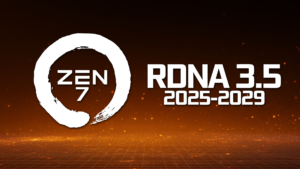


コメント